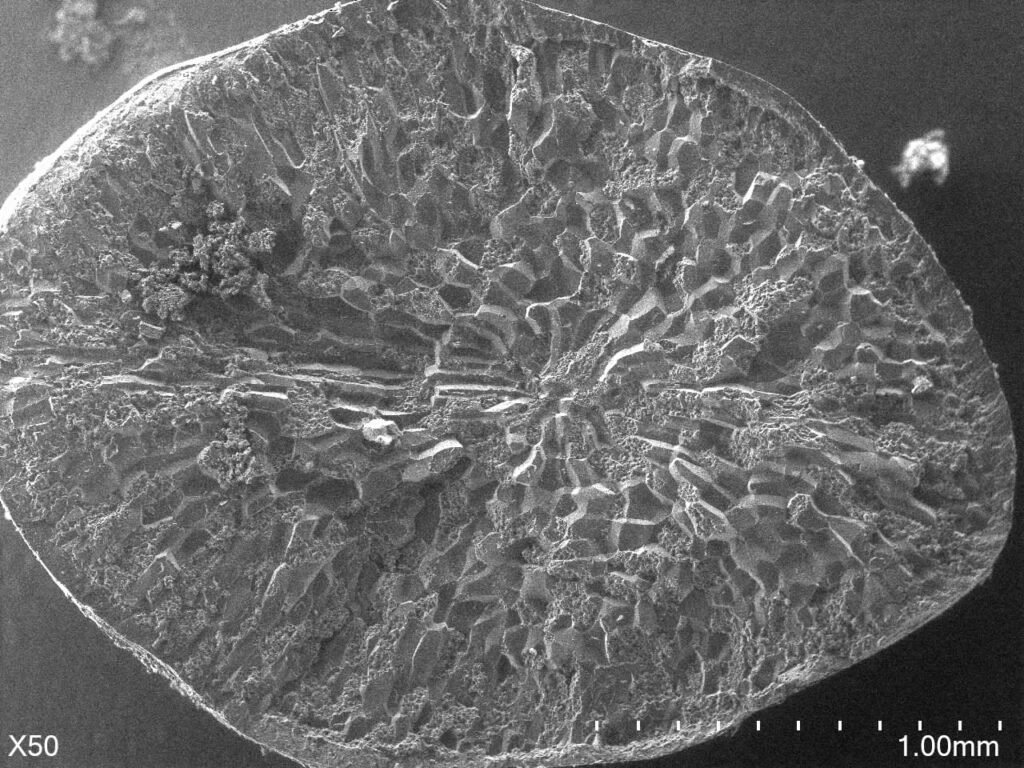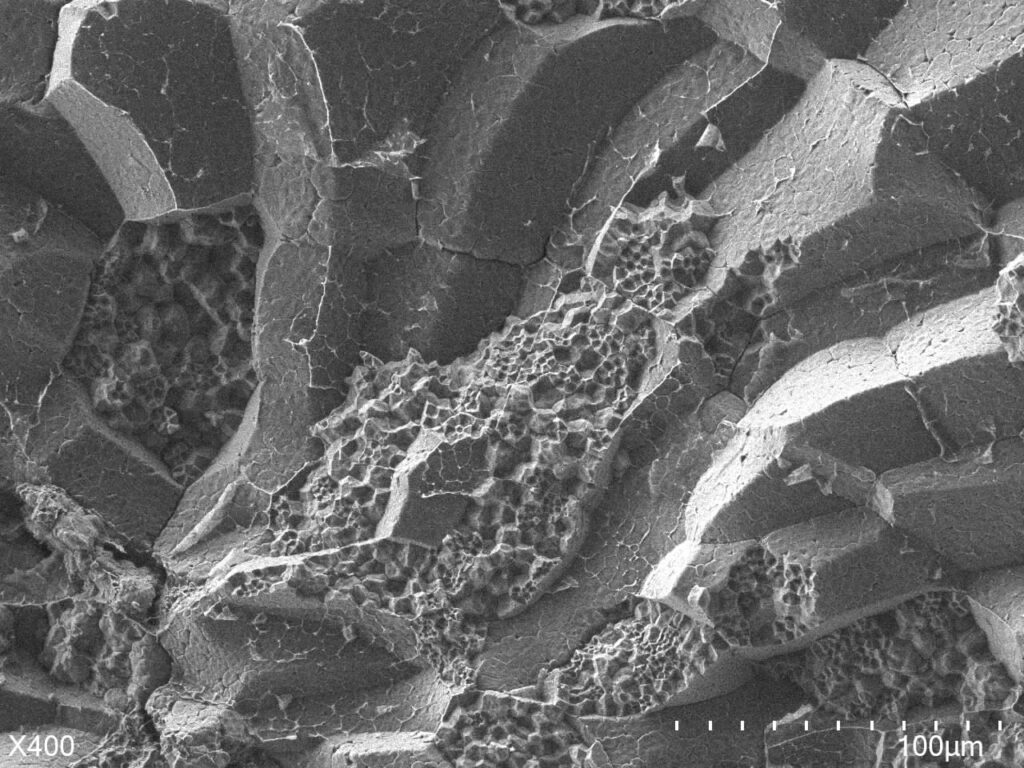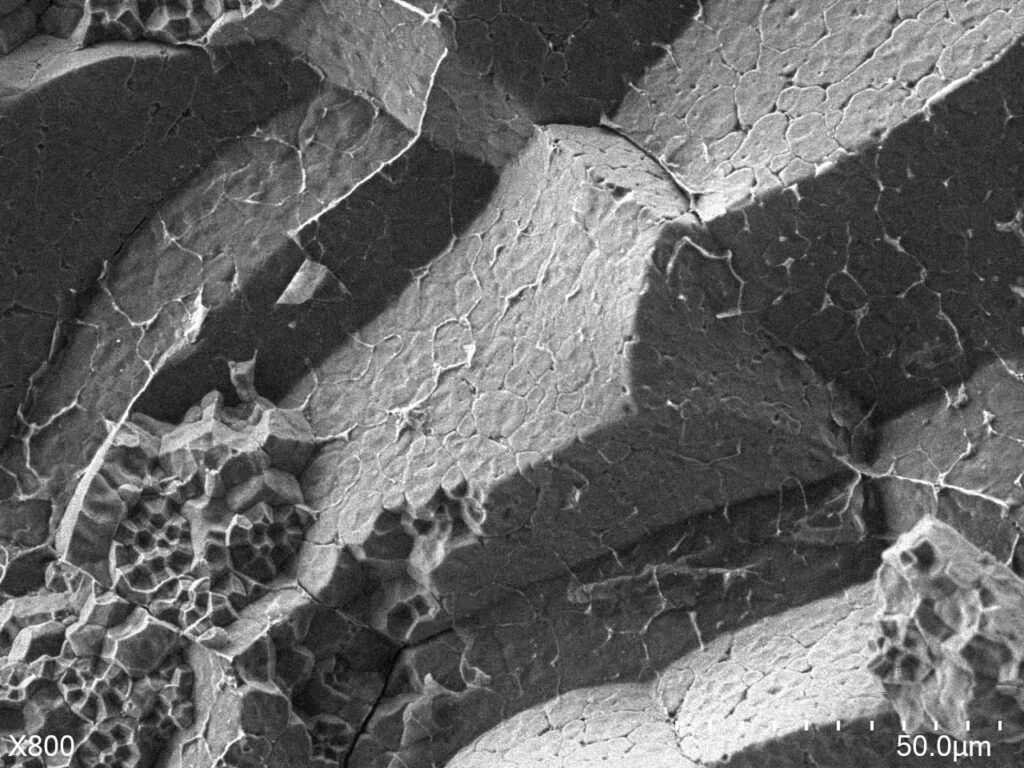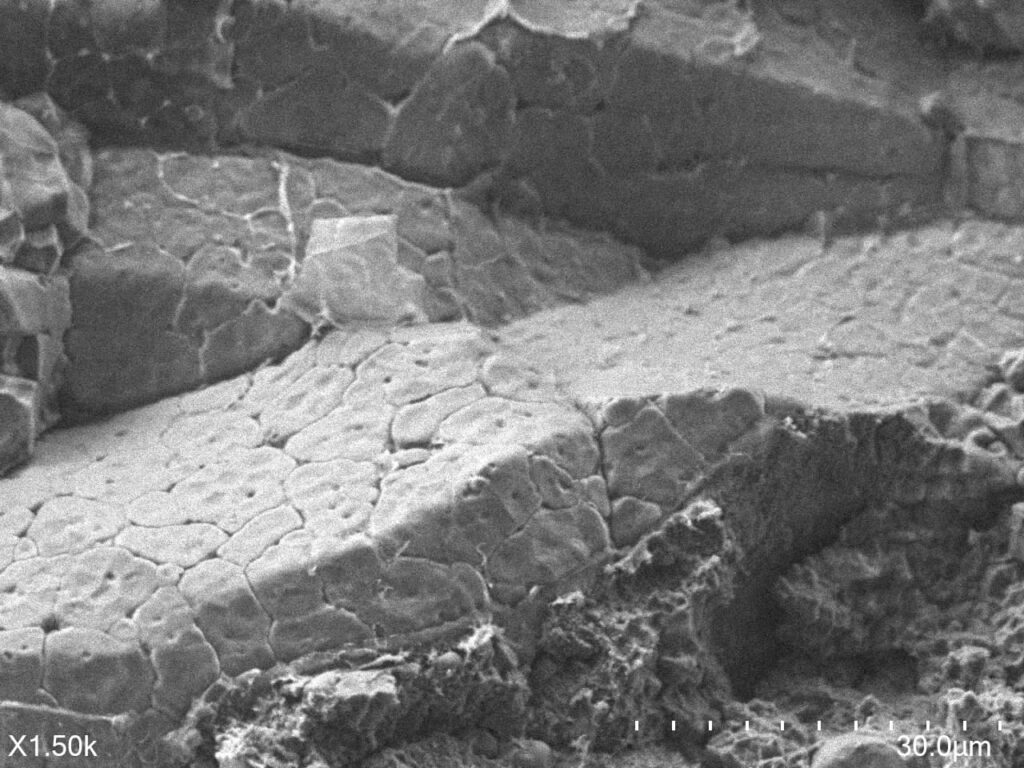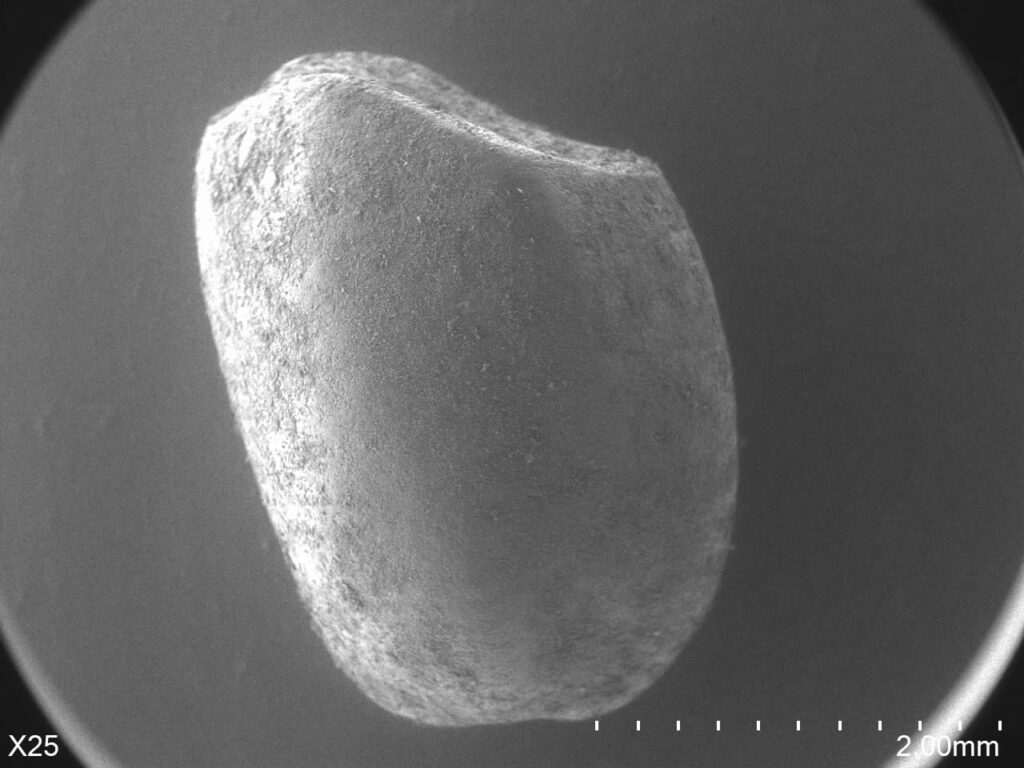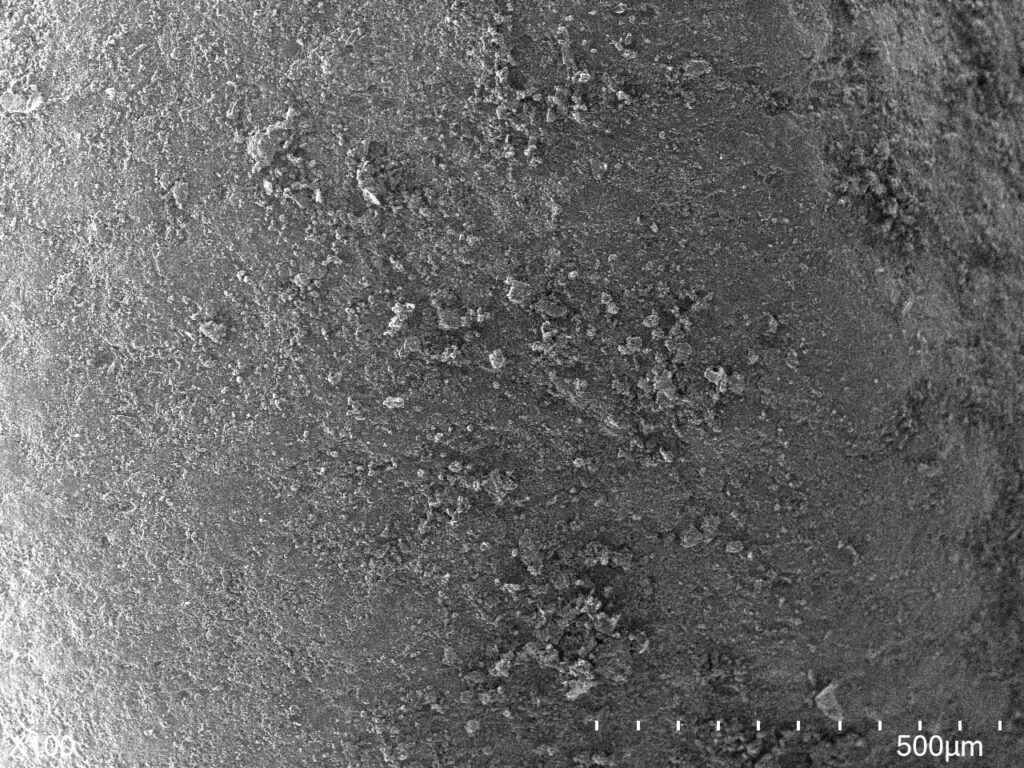ら・べるびぃ予防医学研究所は定期的にzoomでの予防医学セミナー「予医セミナー」を実施しております。
今後の予医セミナーのスケジュールは以下の通りです。
| 日付 | 予医セミナータイトル |
| 2026/2/19 | カルシウムを掘り下げましょう |
| 2026/3/19 | 身近な調剤薬局と薬局 |
※お申込みには予医手帳の無料会員登録が必要です。
予医手帳会員登録後、ログインして「お申込み」メニューより参加したい予医セミナーの「参加する」をクリックしてください。
●申込方法イメージ

また過去の予医セミナー動画見ることはできませんか?とよくお問合せをいただきますので、回答いたします。
当社の「いつも予医ファミリー」という検査のサブスクにご加入いただいている方はいつでも過去のセミナー動画を閲覧いただくことができます。
家族で検査もうけてセミナー動画も見たい、という方はぜひご検討ください。
セミナー動画一覧(敬称略)
| タイトル | 講師 |
| 1.血液検査の見方 | 矢野正生 |
| 2.脂質検査と動脈硬化 | 矢野正生 |
| 3.新型コロナと有害金属・必須ミネラルの関係 | 松本七美 |
| 4.ホルモンと自律神経と血流不足の改善 | 宮澤賢史 |
| 5.飽食の時代における亜鉛不足の現状 | 安田寛 |
| 6.妊活とミネラルの重要性 | 松山夕稀己 |
| 7.血液電解質検査の意義 | 矢野正生 |
| 8.精神疾患と必須ミネラル-セロトニン仮説はもう古い? | 松本七美 |
| 9.断食教室のやさしく分かるファスティングセミナー | 田嶋智子 |
| 10.水銀の話 | 筒井大海 |
| 11.毛髪中ステロイドホルモンとストレス評価 | 保房佳孝 |
| 12.アルミニウムの話 | 筒井大海 |
| 13.心身の慢性不調をスッキリ解消!コルチゾールレベル・リセット法 | ナターシャ・スタルヒン |
| 14.更年期とミネラルバランス | 松本七美 |
| 15.発達障害と有害重金属の関係 | 池田勝紀 |
| 16.有害重金属の影響と検査の話(血液、毛髪、尿、爪) | 池田勝紀 |
| 17.活性酸素と酸化ストレス | 矢野正生 |
| 18.男性更年期と毛髪ホルモン検査 | 保房佳孝 |
| 19.身近な食品添加物 | 米川豊 |
| 20.お腹まわりの脂肪蓄積はコルチゾールのせい? | ナターシャ・スタルヒン |
| 21.自発性と創造力を育む 七田式とモンテッソーリのハーモニー | 藤田祥 |
| 22.毛髪ミネラル検査の質問に回答します。Vol1 | 米川豊 |
| 23.女性に必要な4つの栄養素 | 池田勝紀 |
| 24.PFASってなーに? | 筒井大海 |
| 25.アウトドアと健康 -カラダに効く自然- | 山本将也 |
| 26.検査数値の成り立ち | 矢野正生 |
| 27.食べて伸びる!こどものためのスポーツ栄養セミナー | 佐藤彩香 |
| 28.水の神秘 | 米川豊 |
| 29.鉱物の神秘 Vol.2 | 米川豊 |
| 30.受験合格に大切な栄養療法 | 池田勝紀 |
| 31.不登校対策に大切な栄養療法 | 池田勝紀 |
| 32.小児における有害金属蓄積と亜鉛・マグネシウム不足 | 安田寛 |
| 33.毛髪ミネラル検査から見えてきた予防医学 | 安田寛 |
| 34.身近に潜む有害衣料 | 米川豊 |
| 35.すこやかな日常を取り戻しましょう | 巽 雅彦 |